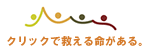試験・団体・香りのお話 > プリニウスの最後 ~ヴェスヴィオの噴火~
プリニウスの最後 ~ヴェスヴィオの噴火~
プリニウスの最後
古代ローマの政治家であり軍人、そして博物誌家であったプリニウス(大プリニウス)。
<博物誌>全37巻を著しました。
そんな偉大な彼の最後の情景です。
第一の手紙
-プリニウスよりタキトゥスに、心からの挨拶を、
(注:このプリニウスは小プリニウス。彼、大プリニウスの甥に当たります。)
あなたはわたしに、伯父の死をより正確に後世に伝える必要から、身近にいたわたしにそれを物語るようにと求めた。あなたの筆によって伝えられるのであれば、伯父の死も不滅の栄光を獲得するのほまちがいない。だからまず、そのことに礼を言いたい。たとえ伯父が、風光明媚で有名だったあの一帯の暇々の瓦疎の下に人知れず死んだとしても、あの忘れることのできない天災によって死んだ人々や埋没した町々と同じく、永遠の記憶に値する存在であることは確かであるからだ。たとえ伯父の後世における栄光が、彼自ら成し遂げた著作によって保証されていようと、それにあなたの筆が加わるならば盤石だ。
いつも考えていることだが、物語るに値する行為を成す才能か、読むに値することを物語る才能かのどちらかを神々より与えられている人は、ほんとうに幸運な人だと思う。だが、より大きな幸運は、その双方ともを与えられた人だ。伯父は、後者の幸運は彼自身の著作で獲得し、前者の幸運は、今やあなたの筆によって獲得するということになる。だからこそ、わたしはこの求めに快く応じよう。いや、あなたにそれを求められたことで、甥のわたしも伯父の名の不滅化に少しでも寄与できることを、心からの喜びともしよう。
あの時期は艦隊の指揮をまかされていた伯父は、基地のあるミセーノにいた。八月二十四日の午後一時前後のことだった。はじめに異変に気づいたのは、わたしの母だった。母は、巨大な黒雲が見えると叫んだ。伯父は、日光浴と冷水浴の後で寝室内で簡単な昼食を済ませ、いつものように机に向っていたのだが、その声に上履きをもって来させてベランダに出た。海のすぐそばの高台に立つ官邸のベランダは、この異例な現象の観察には最適の場所でもあったのだ。
黒雲に似た巨大な噴煙は、高く大きく広がっていた。遠方(ミセーノ岬からは四十キロ以上の距離)からの眺めではどの火山なのかはわからなかったが、それがヴェスヴィオであるのは後になってわかったことだった。そのヴェスヴィオが噴きあげる巨大な噴煙は、傘枡の形をしていた。なぜなら、長い幹は上空めざして高くのびたところで、前後左右に大きく枝分れしていたからだ。爆発によって猛烈な勢いで駆け昇った後で、爆風の勢いが衰えたためか、それとも噴煙自体の重さによるのか、中央部から左右に広がるのだが、それにつれて色合いも変化していた。あるところでは白く、他の部分は灰色で、別のところでは赤黒い色をしていたのだ。この色分けは、押しあげられた火山灰や火砕石の混じり具合によったのではないかと思う。
何ごとにも、好奇心と研究心が旺盛な伯父のことだ。この異例な現象をより近くで観察したい想いに駆られた彼は、小型の快速船を用意するよう命じた。わたしにも、一緒に来たいなら来てもよい、と言った。だがわたしは、伯父から与えられた勉学のほうをつづけたいから家に残る、と答えた。官邸を後に軍港に向おうとしていた伯父に、タスクスの妻のレクティーナからの手紙が届いた。それには、ヴエスヴィオのふもとにある彼らの別荘にも危険が追っていて、逃げるには海からしかないとの訴えが書かれてあった。これで伯父の心は、博物学の研究者から艦隊の司令官に変わった。四股擢ガレー船から或る船隊を、ただちに出港させるよう命じた。自らも、そのうちの一隻に乗船した。知り合いのレクティーーナだけでなく、危険にさらされているにちがいない多くの人々を救助するためだった。あの辺り(おそらくエルコラーノ)は、快適な気候と景観の美しさで、別荘も多く人も多く住む一帯だった。
ミセーノ軍港を後にした船隊は、真東に航路をとった。避難民を満載して逃げてくる多くの船とすれちがったが、ミセーノ艦隊所属の船の舵は危険の場所目指して勣かず、その方角に向って一直線に進んだ。おかげで、見るまに接近してくる噴火最中のヴェスヴィオの怖ろしいまでの全容が、充分に観察できたほどだった。
すでに船の甲板上には、火山灰が降りはじめていた。それは、船隊が接近の度を増すにつれて、より熱く変わり、より量も増していった。それにつづいて、焼けただれた石やまだ燃えている石の塊りが降りそそぐようになった。海岸への接岸は、不可能になっていた。海は、岸に近づくにつれて大波がぶつかる荒れ模様に変わっており、そのうえ、にわかに出現した浅瀬にもはばまれ、火砕流も海ぎわにまで達していたからだ。
それを見た伯父は、一瞬にしろ迷ったらしい。救助を断念して引き返すべきかと考えた.のだろう。だが、後にすべてをわたしに物語った舵手に向い、幸運は勇気ある者を肋ける、と言い、ポンポニアヌスの別荘を目指せ、と命じ針路を変えさせた。ポンポニアヌスの別荘は、そこからは南東の方角にあたるスタビアにあった。だがその頃には、常にはおだやかなナポリ湾全体が大荒れに荒れる海に一変していた。
ポンポニアヌスの別荘では、危険が近づいているのは明らかでもそれはすぐにも襲ってくるとは思っていなかったのか、主人に命じられた召使たちが運びこんだ物でいっぱいになった船は、まだ船着場につながれていた。逆風が収まるやいなや、出港するつもりでいたのだ。そこに伯父が到着したのだが、風向きはいっこうに変わらない。
ポンポニアヌスは、恐怖で心臓が破裂しそうになっていた。伯父はその友を、はげまし力づけたが効果はない。それで、普段の日と変わりはないと思わせるために、二人して入浴し、マッサージもさせ、その後ではともに夕食を愉しんだのだった。
その間にもヴェスヴィオは、溶岩の流れによって稜線が赤く染まり、そのあちこちから火を高く噴きあげていた。夜の闇を背にするようになってからはなおのこと、噴火の様相はより鮮明により光り輝いて見えた。それを眺めて絶望にくれる人々をなぐさめるために、伯父は、あれは住人が消し忘れた火で起きた火災で、山小屋が燃えているのだと説明して歩いた。その後で伯父は、眠りに行った。熟睡であったという。肥満作のおかげで伯父の寝息は大きくうるさかったので、寝室の扉の外でも聴こえた
のである。
だが、しばらくすると、寝室が而している内庭の地面が震勣しはじめ、地表そのものが盛りあがってきた。火山灰や焼けただれた軽石の降りそそぐ量と速度も増す一方になった。もしもそのまま眠りつづけていたならば、寝室の扉のところにまで降り積もった石や灰のために、伯父は二度と外に出ることができなくなっていただろう。起こされて外に出てきた伯父を、一睡もしなかったポンポニアヌスと人々が迎えた。皆の間で、どうしたものかと話し合った。このまま邸内に留まるか、それとも別荘の外に避難するかのどちらかを決めねばならなかった。
別荘も庭も、間断なくゆれ動いていた。地震は、地面全体をひっくり返しでもしたかのようで、立っていることすらも困難になっていた。しかも、ゆれは上下に留まらず、遠ざかったと思えばもどってくるという感じで、いつまでも止まなかった。屋外に避難するにしても、軽量でも火熱をふくんだ火砕石が降りそそぐ下では危険だった。しかし、二つの方法のうちでは、屋外に逃げるほうがまだしも危険の度が低いように思われた。それで、人々は全員、枕やクッションを頭上にのせ、それを長い布で固定させることで、脱出の準備をしたのである。
他の場所では、すでに朝になっているはずだった。だが、ヴェスヴィオから吹きつける風の風下に当ってしまった一帯の人々はまだ、いつもの夜よりもより暗黒の闇の中にいた。ヴェスヴィオが発する大量の火炎と大量の閃光に照らされていながら、闇は少しも薄れることはなかった。人々はその闇の中を、カンテラをかかげて船着場に急いだ。船を出せるかどうかを、自分の眼で確かめようとしてだった。
だが、人々が眼にした海は、前日よりも一段と荒れ、しかも風は逆風のままたった。これでは、別荘にもどるしかなかった。邸内のモザイク張りの床に敷布を敷かせ、伯父はその上に横になった。そのままの姿で二度、冷たい水を所望し、それを飲んだ。そのうちに、強い硫黄の匂いのする灰をふくんだ大気が、音もなく周囲を満たしはしめた。人々は逃げ出した。二人の召使にささえられて、伯父も起き上がった。だが、すぐに倒れ、そのまま息を引きとった。わたしの想像では、噴火によって発生したガスによる呼吸困難が原因ではなかったかと思う。常日頃から伯父は、呼吸器系が弱かった。
昼の光がもどってきたとき、それは伯父が最後に陽光を見た日から三日後だったが、もどってきた人々が見た伯父は、倒れたときと同じ姿をして横たわっていた。損なわれた箇所もなく、衣類もあのときに着けていたままで乱れもなく、死体というよりも眠っている姿に見えたという。
その間ミセーノでは母とわたしは……。いや、このようなことは歴史とは無関係であり、それにあなたが知りたいと求めたのは、伯父の死の真相である。だから、筆もここで置く。しかし、これだけはつけ加えよう。ここで語った事柄のすべては、わたし自身が現場にいて見た事実か、それとも、現場にいた者があの直後に、わたしに逐一物語ったことのみであることを。
これらの事柄の中で何をとりあげ何を捨てるかは、あなたの考えしだいであることは言うまでもない。手紙を書くことと歴史を吉くことは、同じではない。友人に向って書くのと、公衆に向って書くのとでは、ちがって当然なのだから。
第二の手紙
-プリニウスよりタキトゥスに、心からの挨拶を、
あなたはわたしに、伯父の死の真相を語った前の手紙で書きかけて止めたことを、つづけて物語れと言う。つまり、ミセーノに残ったわたしが、どのような不安に苦しみ、どのような危険に遭遇したかを話せというわけだ。
「たとえわが心に、不幸で怖ろしい想い出が再びよみがえろうとも、あえて物語ろう」(ヴェルギリウス作の『アエネイアス』の一句)。
伯父が船で発った後のわたしは、夕暮までの聞を勉学に没頭した。伯父に同行しなかったのは、勉学をつづけるためであったのだから。勉学を終えた後で、いつものように入浴し、その後で夕食をとり、眠りに行った。短くて浅い眠りだった。地震で邪魔されたからだが、地震は珍しくないカンパーーニア地方なのに、その夜の地震は特別だった。単なる震動ではなく、崩れ落ちてくるような激しい動きであったからだ。
母が、わたしの部屋に駆けこんできた。わたしのほうも、寝床から起き上がったところだった。二人とも、同じことを考えたのだ。もしもまだ眠っているのなら、起こすべきだと考えたのだった。
母とわたしは、内庭の一角に坐った。その内庭は、少し歩けば海岸に通じていた。わたしは、勇気があったのか、それとも無分別のためか(なにしろまだ十八歳だった)、ティトゥス・リヴィウスの一巻を持ってこさせ、他に何もすることがないままに読みはしめた。それも、ただ単に読むのではなく、要点を書き出しながら説んたのだ。スペインから来て邸内に滞在中の伯父の友人が、庭に坐る母とそのそばで勉学中のわたしを見て憤慨し、わたしに対してはわたしの平静さを、母に対してはそういう息子を許すのん気さを非離した。わたしは、それにはかまわずに読書をつづけた。
こうしているうちに、朝になった。だが、いまだ弱々しく不破かな朝の光で見る周囲の家は、そのほとんどが崩れ落ちていた。われわれの住むヴィラは、周囲から離れた高台にあり、華麗ではなくても大きく堅固な造りだったが、崩れ果てた周辺を見た後ではこの家でも安全とは思えないという、家人たちの心配は当然でもあったのだ。
そこでわれわれは、ついに屋外に避難することに決めた。ヴィラから出て郊外に向って歩みはじめたわれわれのコ打に、途方にくれた附近の住民たちも従いてきた。恐怖の中では、自分の考えを貰くよりも他人の決めたことに従うほうが賢明に思えるものだ。というわけで、召使たちを従えたわれわれ一行の後にはさらに人々の長い列がつづくことになった。
家並がつきる町の外まで来たところで、われわれ一行はひとまずにしろ歩みを止めた。そこでも多くの異常なことが起こって、わたしたちを驚かせ怖れさせた。貴重品やとりあえずの必需品を積みこんで従いてきていたわが家の荷車が、道は完全に平坦であるのに、あちらに動いたと思えばこちらに動くという調子で、停止させておくことができなくなったのだ。車輪の両脇を石ではさんでも、まったく用をなさなかった。
それに、眼下に広がる海もいつもとはちがった。海水が沖合にまで引いた後の砂浜一面に、とり残された魚や貝が散らばっていた。その向うは、怖ろしいまでに黒く巨大な雲でふさがれていた。その巨大な噴煙は、絶え間なく噴きあがる火炎で彩られ、まるで闇夜に輝く巨大で強烈な雷光を見ているようだった。
それに眼を奪われて立ちつくしていた母とわたしのところに、前に述べたスペインから来ていた伯父の友人が近寄ってきて叫んだ。「もしもあなたにとっては兄の、きみにとっては伯父のプリニウスが生きているとしたら、何よりもの心配はあなた方二人の安全だ。もしも不幸にして死んだとしても、何よりもの心残りがあなた方二人の無事であることでは変わりはない。避難するのに、何をためらっているのか」
母とわたしは、伯父の消息がわかるまではわれわれ二人の安全を考えることなど出来ないと答えた。彼は、もはや何も言わずにわれわれから離れ、一人で避難して行っ それから少しして、噴煙が海上全体をおおいはじめた。すでにカプリ島は視界から消えていたが、今では近くのミセーノ岬までが見えなくなった。それを見た母はわたしに、逃げるようにと言った。おまえは若いのだから逃げられる、年齢も老い肉体も老いたわたしは、おまえの死の原因にならなかったというだけでも安らかに死ねるのだから、と言って、わたしに逃げるよう説く口調はもう哀願だった。わたしはその母に向って、母上とともでないかぎり助かるつもりはないと、くり返して答えた。そして、母の手をとり、急ぎ足で歩きはじめた。母はかろうじて従いてきたが、歩みが遅れるのはわたしのせいだと、自分で自分を責めるのはやめなかった。
その頃には、火山灰までが降りはじめていた。奇妙な予感で思わず振り返ったわたしの眼に、濃い霧状のものが、まるで川からあふれ出た水が地上を満たしていくように、背後から迫りつつあるのが見えた。わたしは母に言った。「道をはずれましょう、後から来る人々に押しつぶされないためにも」
わたしたち二人は、道から離れ逃げる群衆からも離れたところまで行き、そこでようやく身体を休めることができた。すでに夜に入っていた。だが、夜といっても、月のない夜でもなく、雲がかった夜でもなかった。灯一つない閉めきった部屋の中にでもいるような、奇妙な感じの夜だった。その暗闇の中に、叫び声だけがとび交っていた。女たちが嘆き悲しむ声、子供たちの泣き叫ぶ声、男たちの怒鳴り声。親を探す声、子を呼ぶ声、妻を夫を、声で聴き分けようとして呼びかける声。ある者は自分だちの運命を嘆き、他の者は肉親を襲った不幸を嘆き、別の者は、死への怖れのためにかえって死を呼ぶ。多くの人は両手を上にあげて神々に祈っていたが、それと同じくらいの数の人が、もはや神々はいない、この闇は永遠につづいて世界の終末に至るのだと叫んでいた。
恐怖と絶望によって曲げて伝えられた情報が、ほんとうの害につながる例も不足しなかった。ミセーノの一つの建物は崩壊し、もう一つの建物は火炎に包まれていると伝えられた。いずれも背情報だったが、あのときは誰もが信じたので、絶望はより高まった。
周囲が、少しばかり明るくなった。だがそれは、朝が訪れたからではなくて、火災が原因だった。幸いにも火災は、遠方で止まってくれた。しかし、灰が降ってきたのだ。今度は、濃くて重い火山灰の雨たった。われわれはしばしば立ち上がって、それをふるい落さねばならなかった。それを怠ればたちまちにして灰におおわれ、灰の重さに押しつぶされてしまいそうだった。あのときのわたしが、人々の恐怖に染まって動揺し、それによって群衆に混じっての避難行に加わらなかったことを、また、悲嘆にもくれず、絶望の叫びもあげずに冷静に行動できたことを、当時のわたしの年齢を思えば、自分で自分を賞めてやりたいくらいだ。あのときのわたしは、他の多くの人とともに自分が死ぬであろうとは、また、これまでの短い一生、これからの長く大きな可能性のすべても今ここでわたしとともに失われるとは、少しも頭に浮んでこなかったのだから不思議である。あのときの状態を考えれば、生きるよりも死ぬほうが、より大きな安らぎをもたらしたであろうに。
灰をふくんだこの濃霧は、それでもついには薄らぎ、単なる煙の雲に変わった。その後ではじめて陽光がもどってきた。だが、この日は太陽自体も薄明るく、日蝕のときのようだった。われわれには、周囲のあまりの変わりようが信じられなかった。見えるものすべては、雪が降りつもったかのように、灰の下に埋もれていたのだから。
わたしは、母を連れ召使たちをせき立ててミセーノにもどった。邸内に足を踏み入れてまずやったことは、疲れきった身体を体ませることだった。その夜も、恐怖と希望の入り混じった中で過ぎた。地震がいっこうに止まないこと、いやこれ以上にひどくなることへの恐怖は、振り切ることはやはりできなかった。いつものわたしだったら、人々が怖ろしがる予兆などは笑いとばしたものであったのに。しかし、もはやどれほど大きな不安や恐怖にさいなまれようとも、わたしと母の気持は決まっていた。伯父の消息を待って、それがもたらされるまでは絶対にここから勣かないと、固く決めたのだった。
小プリニウスのこの二通の手紙がどのように使われたかは、タキトゥス著の『同時代史』中のこの時期の叙述が中世を経るうちに失われてしまったために、知ることができないのは残念と言うしかない。
以上、~塩野七生 ローマ人の物語<危機と克服>~より抜粋しました。
Topへ↑